納品日:2019-12-26
都道府県:東京
メーカー:FUJIFILM
機種名:DocuCentre-VI C2264
![]()
![]()

コピー機を使っていて、こんな「変な音」が気になることはありませんか?
コピー機の異音でよくあるお悩み:
コピー機の異音を放置して使い続けると、部品の破損や紙詰まりの増加、最悪の場合は故障や業務停止につながるリスクもあります。一方で、すぐに壊れるわけではない軽い異音もあり、どこまで様子見をしてよいのか判断がつきにくいのも事実です。
この記事では、コピー機から聞こえる「音の種類」と「発生タイミング」別に、まず確認したいポイントと自分でできる簡単なチェック方法を整理します。
さらに今すぐ使用を止めるべき危険なサインと、保守に任せるべきラインをわかりやすく解説し、異音がしたときでも落ち着いて対応できる判断の目安をお伝えします。
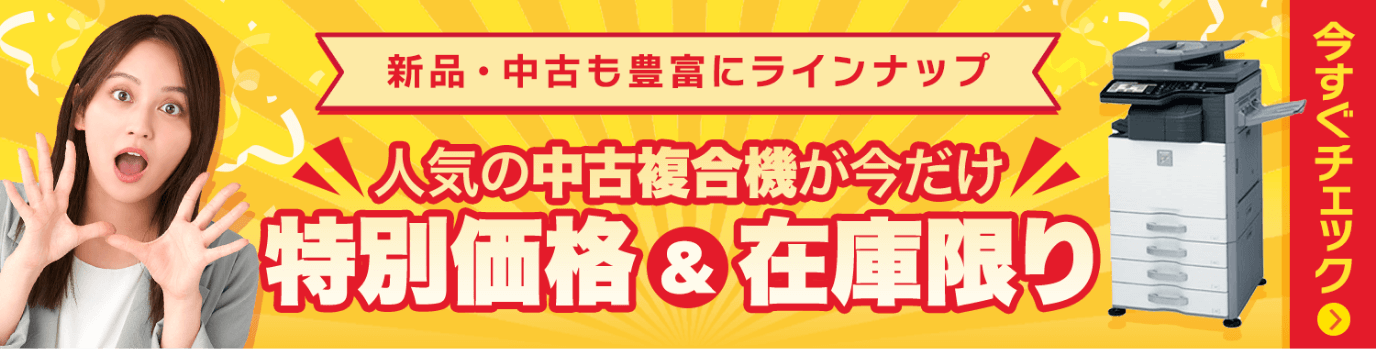

監修者
千々波 一博
(ちぢわ かずひろ)
保有資格:Webリテラシー/.com Master Advance/ITパスポート/個人情報保護士/ビジネスマネージャー検定
2004年から通信業界で5年間営業として従事。その後、起業して他業種に進出。OFFICE110に営業で入社し、月40~60件ほどビジネスホン・複合機・法人携帯などを案内。現在は既存のお客様のコンサルティングとして従事。
2004年から通信業界で5年間営業として従事。その後、起業して他業種に進出。OFFICE110に営業で入社し、月40~60件ほどビジネスホン・複合機・法人携帯などを案内。現在は既存のお客様のコンサルティングとして従事。
コピー機からいつもと違う音がしたときは、「壊れたかどうか」よりも先に、まず安全面を確認することが大切です。
コピー中や印刷中に「ガガガ」「ギィギィ」といった聞き慣れない音がすると、不安になりついそのまま様子を見てしまいがちです。しかし、音の種類や大きさによっては部品の破損や発煙など、思わぬトラブルにつながる可能性があります。
このセクションでは、コピー機から異音がしたときにまず確認したいポイントと、「今すぐ使用を止めるべきケース」と「様子見してよいケース」の目安を整理します。
金属同士がこすれるような大きな音や、バキッと何かが折れたような音がしたときは、すぐにコピー機の使用を停止してください。
コピー機内部の部品が欠けていたり、固定が外れていたりすると、「ガリガリ」「ギギギ」といった強い異音が続くことがあります。そのまま運転を続けると、部品の破損が進んだり、紙詰まりや発煙などのトラブルにつながるおそれがあります。
異音とあわせて、焦げたようなにおいがする、内部から煙のようなものが見える、エラーコードが頻繁に表示されるといった場合も要注意です。こうした危険な異音のサインが出ているときは、無理に再起動したり自分で分解したりするのは避けましょう。
今すぐ使用を止めたい異音の目安:
これらの症状がある場合は、電源ボタンでコピー機の電源を切り、可能であればコンセントも抜いてください。そのうえで、保守会社や購入元に状況を伝え、点検や修理の手配を依頼することをおすすめします。
小さな「コトコト」「カタカタ」といった音で、印刷結果に問題がない場合は、まず周辺や設置状況を確認しながら様子を見ることもできます。
コピー機は、ファンの回転音やギアの駆動音など、通常でもある程度の動作音が出ます。床がわずかに傾いていたり、キャスターのロックが外れていたりすると、本体の揺れに合わせて軽い「カタカタ音」が出るケースもよくあります。
また、給紙トレイがしっかり閉まっていなかったり、本体に接触しているケーブル・備品が振動して「コトコト」と鳴っているだけの場合もあります。こうした軽度な異音で、印刷物に汚れやかすれがなく、エラー表示も出ていないようであれば、次のような簡単なチェックから始めてみてください。
様子見できる異音の目安とチェックポイント:
これらの確認を行っても違和感のある音が続く、音が徐々に大きくなってきた、印刷結果がおかしくなってきたといった場合は、軽度の異音であっても自己判断で使い続けるのは避けたほうが安心です。その際は、早めに保守窓口に相談し、専門スタッフによる詳細な診断を受けるようにしましょう。
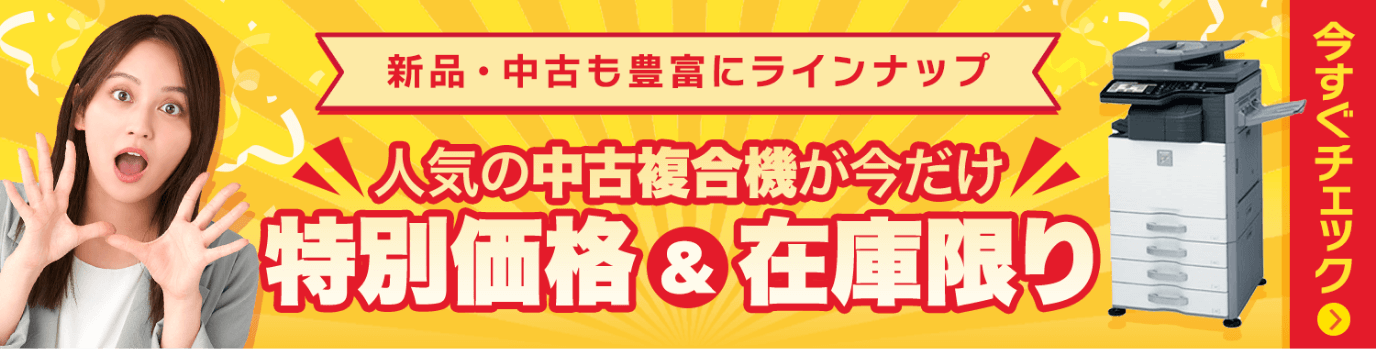
コピー機から聞こえる異音は、音の種類によってある程度、原因の方向性を絞り込むことができます。
「ガガガ」「バタバタ」「キュルキュル」「ギィギィ」など、異音のパターンを意識して聞き分けることで、給紙まわりなのか、ローラーなのか、内部部品なのかといった切り分けがしやすくなります。大まかな当たりを付けておくと、保守窓口に相談するときの説明もスムーズです。
このセクションでは、よくある異音を「ガガガ・バタバタ」「キュルキュル」「ギィギィ・キィー」の3種類に分け、それぞれの代表的な原因と利用者が確認してよいポイントを整理します。
「ガガガ」「バタバタ」といった断続的な音がするときは、給紙まわりのトラブルを疑ってチェックするのが基本です。
用紙がうまく送られていないときや、給紙トレイの差し込みが浅いときには、紙がひっかかるような「ガガガ」という音が出ることがあります。また、用紙のサイズや種類が設定と合っていない場合も、ローラーが空回りしたり、紙端を強くたたくような「バタバタ」音が出るケースがあります。
「ガガガ」「バタバタ」音がするときのチェックポイント:
これらを確認しても大きな音が続く場合や、紙詰まりが頻発する場合は、内部のローラーや部品に原因がある可能性があります。その場合は無理に繰り返し印刷せず、保守窓口に相談して点検を依頼してください。
▼ 紙詰まりトラブルの原因と対処法を詳しく知りたい方はこちら
「キュルキュル」「キュー」という細く続く音がする場合は、紙送りローラーや内部ベルトの劣化が疑われます。
長期間使用していると、ゴム製のローラーが硬くなったり、ベルトのテンションが変化したりして、回転部分から擦れるような「キュルキュル音」が出ることがあります。特に、印刷開始時や連続印刷の途中で一定のリズムで「キュー」と鳴る場合は、内部の駆動系に負荷がかかっているサインかもしれません。
「キュルキュル」音がするときに確認したいこと:
ローラーやベルトの劣化・調整は、内部の分解作業を伴うことが多いため、利用者自身での対応はおすすめできません。音の傾向と発生タイミング、印刷結果の状態を整理したうえで、保守会社に相談し、交換や調整の可否を確認しましょう。
「ギィギィ」「キィー」といった高く長く続く音は、内部部品の摩耗や潤滑不良によって発生している可能性があります。
内部のシャフトやギア、ヒンジ部分など、金属や樹脂の接触部は、長期の使用で少しずつ摩耗したり、グリスが減って滑りが悪くなったりします。その結果、動作のたびに高いこすれ音が出ることがあり、ドアの蝶番がきしむような音に近い印象になることもあります。
「ギィギィ」「キィー」音が続くときの着目点:
内部部品の摩耗や潤滑不良は、放置すると徐々に悪化し、別の部品への負荷増加や、最終的な故障につながる場合があります。自分で潤滑剤を差したり、部品に手を加えたりするのは避け、音の種類や発生状況をメモしたうえで、早めに保守点検を依頼することが安心です。
コピー機から異音がしたときは、「どんな音か」と同じくらい「いつその音が出るか」を意識しておくことが大切です。
起動直後だけ音がするのか、印刷中の給紙・排紙のときだけなのか、あるいはスキャンやADF(自動原稿送り)を使ったときだけなのかによって、原因として疑うべき箇所が変わってきます。タイミングと音の特徴をセットでメモしておくと、保守窓口への説明もしやすくなります。
このセクションでは、「起動時」「給紙・排紙のとき」「スキャン・ADF使用時」の3つのタイミング別に、よくある原因と利用者が確認してよいポイントを整理します。
コピー機の電源を入れた直後やスリープ復帰時だけ異音がする場合は、自己診断やウォームアップ動作に関連しているケースが多くなります。
起動時には、ファンの回転や各部のモーター動作、内部部品の初期位置合わせなど、普段の印刷中とは異なる動作が集中します。そのため、起動直後だけ「ウィーン」「ガコン」といった音が一時的にするのは、正常な範囲であることも少なくありません。
一方で、今までしなかった「ガリガリ」「ギギギ」といった大きな異音が、起動するたびに毎回続くようになった場合は注意が必要です。内部の駆動部やファンにほこりが溜まっていたり、部品の固定が甘くなっていたりする可能性があります。
起動時の異音で確認したいポイント:
短時間の動作音で印刷には問題がない場合は、しばらく様子を見る選択肢もありますが、明らかに大きな音が続くときや、エラー表示を伴う場合は、早めに保守窓口に相談して点検を依頼することをおすすめします。
用紙を送り出したり排紙したりするときだけ異音がする場合は、紙の搬送経路に原因があることが多いです。
給紙ローラーや搬送ローラーのすべり、用紙の角がひっかかる状態、トレイのセット不良などがあると、「ガガガ」「バタバタ」「キュッ」といった音が、給紙・排紙のタイミングで集中的に発生します。また、用紙のサイズや種類が設定と合っていないと、紙詰まりや搬送不良が起こりやすくなり、異音の原因になることがあります。
給紙・排紙時の異音で確認したいポイント:
これらを見直しても給紙・排紙のたびに大きな異音が続く場合や、紙詰まりが繰り返し起こる場合は、ローラーの劣化や内部部品に問題が出ている可能性があります。自分で原因を特定しようと無理に触らず、状況を伝えたうえで保守会社に相談し、点検や部品交換の要否を確認しましょう。
原稿ガラス面でのスキャンや、ADF(自動原稿送り)を使ったときだけ異音がする場合は、スキャンユニットやADFまわりに原因があるケースが考えられます。
原稿台でのスキャン中に「ギーッ」といった横方向の動きに合わせて音が出る場合は、読取りユニットを動かすレールやモーター部の摩耗・汚れが影響していることがあります。また、ADF使用時に「ガガガ」「バタバタ」といった音がする場合は、原稿送りローラーの劣化や、原稿の重なり・折れなどが影響している可能性があります。
スキャン・ADF使用時の異音で確認したいポイント:
簡単な清掃や原稿の差し替えで改善するケースもありますが、異音が続いたり、読取り結果にスジや欠けが出るようになったりした場合は、スキャンユニットやADFの部品交換が必要になることもあります。その際は、自分で分解や調整を行うのは避け、異音の状況とスキャン結果の状態を整理して、保守窓口へ相談することが安心です。
▼ コピー機トラブル全般の対処方法を詳しく知りたい方はこちら
コピー機の異音に気づいたときは、「自分で確認してよい範囲」と「専門の保守に任せるべき範囲」を切り分けることが大切です。
むやみにカバーを開けたり内部に手を入れたりすると、かえって故障を広げてしまったり、安全面でリスクを高めてしまうことがあります。一方で、設置状況やトレイの状態など、利用者側で簡単に見直せるポイントも少なくありません。
このセクションでは、利用者が安全に行える応急チェックと、分解に近い作業や危険を伴う状況など、保守に任せるべきラインをわかりやすく整理します。
異音がしても、設置場所やトレイ・用紙の状態を確認する程度であれば、利用者が安全に行える応急チェックの範囲です。
まずはコピー機本体がぐらついていないか、床が大きく傾いていないかを確認します。キャスターのロックが外れていると、本体が少し動くだけで「カタカタ」といった異音が出ることがあります。必要に応じてロックをかけ直し、安定した場所に置き直しましょう。
次に、給紙トレイやカセットが最後までしっかり差し込まれているか、用紙が規定枚数を超えて積まれていないかを確認します。用紙サイズや用紙種類の設定が実際の紙と合っているかを見直すだけでも、給紙まわりの異音が改善するケースがあります。
利用者が行ってよい代表的な応急チェック:
これらのチェックは、工具を使わず、無理に力を加えない範囲であれば大きなリスクはありません。それでも異音が改善しない場合や、異音が徐々に大きくなっていく場合は、無理に自分で対処を続けず、早めに保守会社や販売店へ相談するようにしましょう。
▼ コピー機の日常メンテナンス方法を詳しく知りたい方はこちら
カバーを外して内部部品に触れたり、ネジを外して分解に近い作業を行ったりするのは、利用者が行うべき範囲を明らかに超えたNG行為です。
内部のローラーやギア、配線部分は、感電リスクや火災リスクを避けるための安全設計がされています。そこへ自己判断で潤滑剤を吹き付けたり、掃除機やエアダスターで強い風を当てたりすると、思わぬ故障や安全上のトラブルにつながるおそれがあります。
また、異音に加えて焦げたようなにおいがする、内部から煙が出ている、ブレーカーが落ちる、同じエラーコードが繰り返し表示されるといった場合も、利用者側の対応ではなく、直ちに保守に任せるべき状況です。
分解に近いNG行為と、保守を呼ぶ目安:
このような状況では、まずコピー機の電源を切り、可能であればコンセントも抜いたうえで、保守窓口や販売店へ連絡してください。その際、異音の種類・発生タイミング・直前の操作内容を簡単にメモして伝えると、原因特定や対応方針の判断がスムーズになります。

オフィスのコピー機の異音が気になったときは、トラブルが大きくなる前に私たちOFFICE110へご相談ください。
私たちは、単にコピー機を販売するだけでなく、導入前のご相談から設置、運用中のトラブル対応、入れ替えのご提案まで、一連の流れを通してサポートしています。「修理を続けるべきか、買い替えを検討すべきか」など、判断に迷う場面でも、台数や印刷枚数、保守状況を踏まえた現実的な選択肢をご提案できます。
OFFICE110にご相談いただくメリット:
「今使っているコピー機をこのまま使い続けて大丈夫か」「どのタイミングで入れ替えるべきか」など、気になる点があれば、まずはお気軽にOFFICE110までご相談ください。
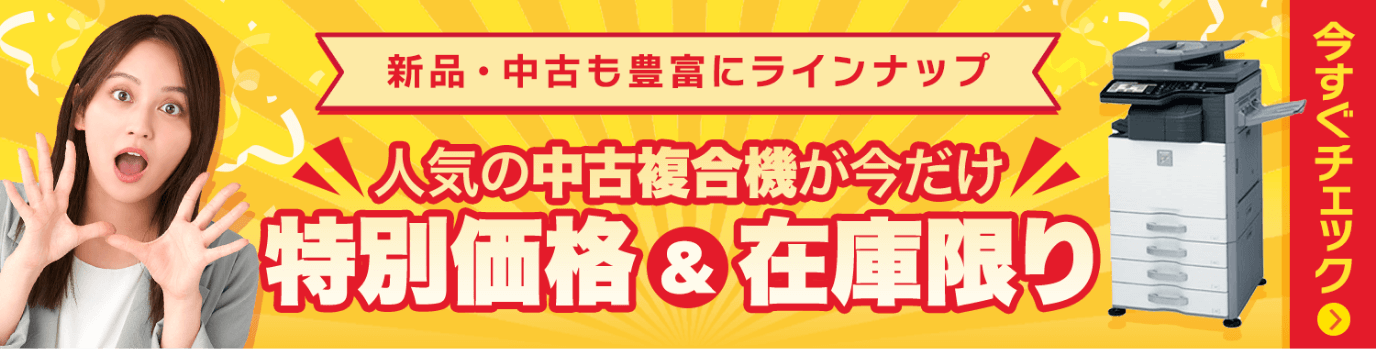
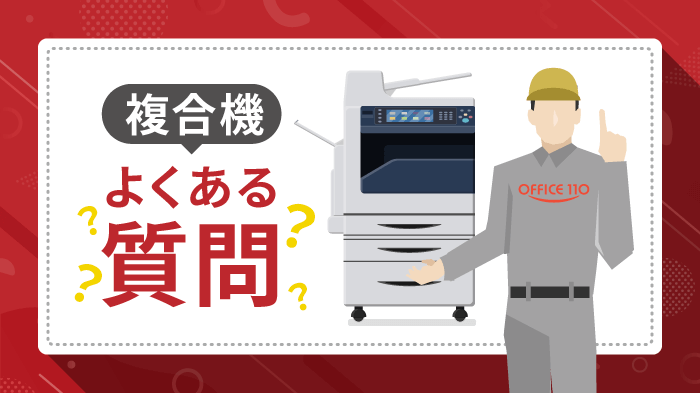
コピー機からいつもと違う音がしたら、「どんな音がするか」「いつその音が出るか」を落ち着いて確認し、無理に使い続けないことが重要です。
金属がこすれるような大きな音や、におい・煙を伴う異音がある場合は、ただちに使用を中止し、安全を優先して保守に連絡する必要があります。一方で、軽い「コトコト」「カタカタ」程度の音であれば、設置状態や給紙トレイ、用紙設定などを見直すことで改善するケースもあります。
異音の種類や発生タイミングをメモしておくと、保守窓口に相談したときに原因の絞り込みがスムーズになり、適切な対応につながりやすくなります。自己判断で分解や調整を行わず、専門家のサポートを早めに受けることが、コピー機を長く安全に使ううえでのポイントです。
小さな異変のうちに確認と相談をしておくことで、業務への影響や故障リスクを最小限に抑え、コピー機を安心して運用し続けることができます。
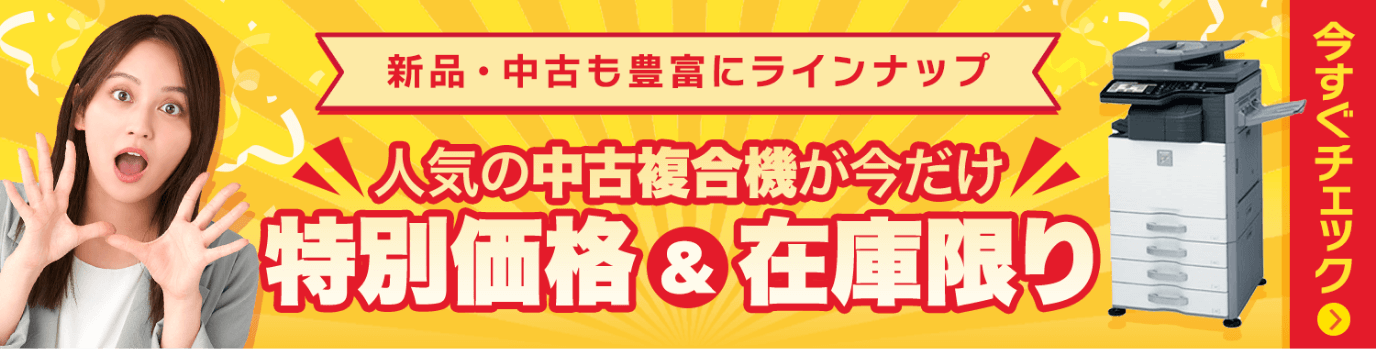


お問い合わせ後、
内容のヒアリング

見積書・保守契約の説明
各種資料の提出

納品日の日程調整

設置工事~完了

ご納得頂けるまで何度で
も対応いたします。
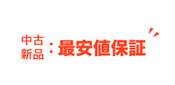
中古は新品同様までクリ
ーニングをしたS級品。

工事費も業界最安値で
ご提示します。

各種お支払い方法をご
用意しました。