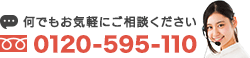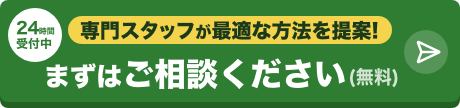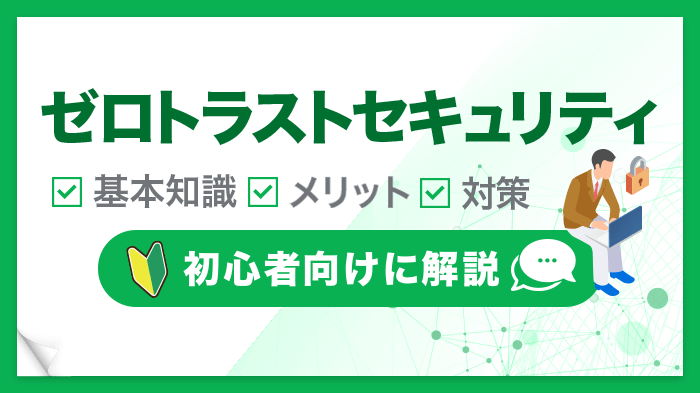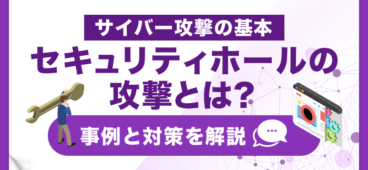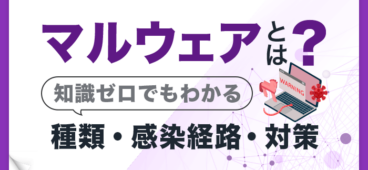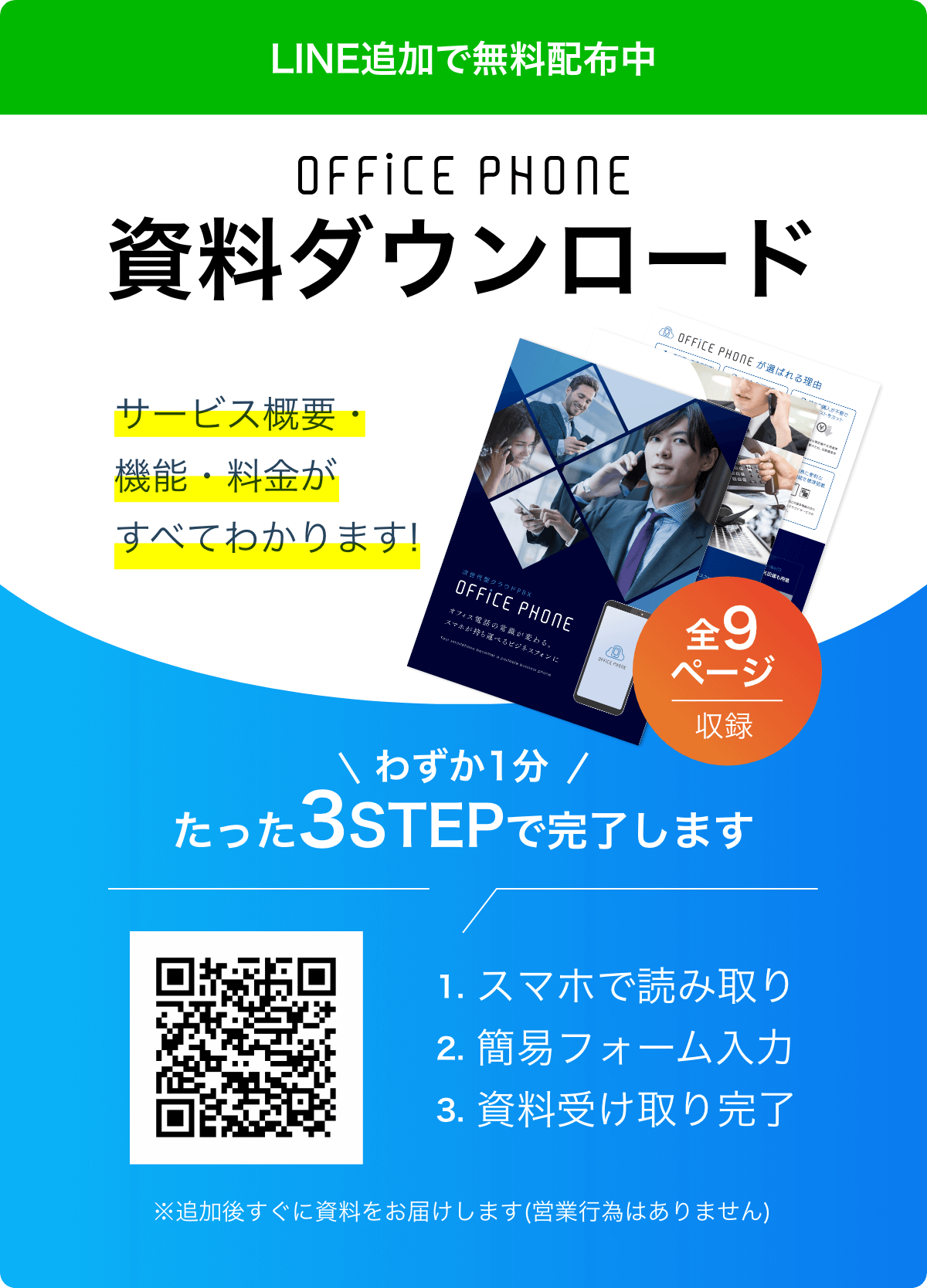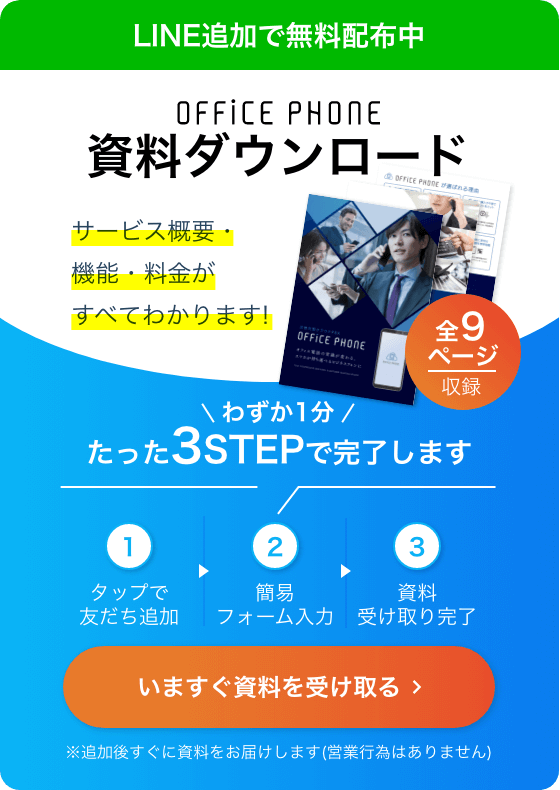情報セキュリティの3要素とは?最新の7要素もわかりやすく解説
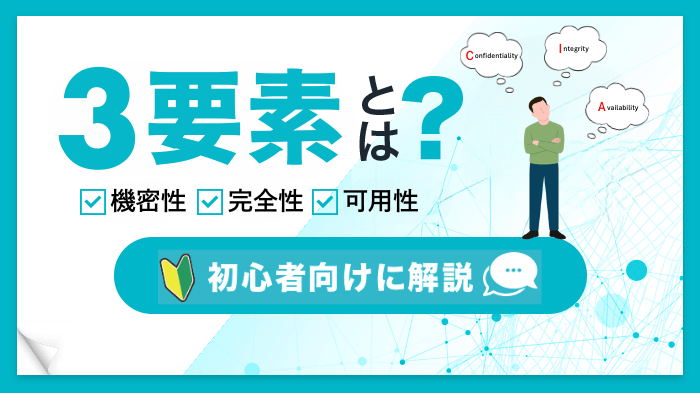
情報セキュリティの3要素(機密性・完全性・可用性)とは、企業の情報資産を守るための基本的な考え方です。
サイバー攻撃の高度化が進む中、とくに中小企業では情報漏えいや業務停止といった深刻な被害が相次いでいます。
こうしたリスクに備えるには、まず3要素を正しく理解し、自社の弱点を把握することが不可欠です。
近年では、従来の3要素に4つの視点を加えた「7要素」の考え方も注目されています。
本記事では、情報セキュリティの基本から最新の7要素までをわかりやすく解説します。
情報セキュリティの基本と3要素・7要素の全体像

情報セキュリティを考えるうえで、最初に押さえておきたいのが「3要素」と呼ばれる基本的な考えです。
これは、情報を安全に扱うために不可欠な機密性・完全性・可用性の3つを指します。
それぞれの要素がどのような意味を持ち、どんな対策と関係するのか理解することで、自社に必要なセキュリティ対策が見えてきます。
そもそも「情報セキュリティ」とは?
情報セキュリティとは、個人や企業が扱う重要な情報を、不正アクセスや漏えい、改ざんといったさまざまな脅威から守るための仕組みや取り組みを指します。
守るべき情報には、顧客の氏名や住所、クレジットカード情報、取引先との契約書、社内のマニュアルや売上データなどが含まれます。
こうした情報が第三者に流出した場合、悪用されるリスクがあるだけでなく、企業の信頼が損なわれ、損害賠償や業務停止といった深刻な影響を招くおそれがあります。
テレワークやクラウドの活用が進む昨今、社外から情報へアクセスする機会も増えており、情報セキュリティへの意識や対策の徹底は、すべての企業にとって欠かせないものとなっています。
情報セキュリティの3要素(CIA)とは?
情報セキュリティの基本を支えるのが「機密性(Confidentiality)」「完全性(Integrity)」「可用性(Availability)」の3つの要素です。
これらは英語の頭文字をとって「CIA」と呼ばれ、セキュリティ対策を考えるうえで最初に理解すべき考え方です。
この3要素を理解すれば、自社のセキュリティ対策で、特に補強すべきポイントが明確になります。
それでは、それぞれの要素について、詳しく見ていきましょう。
機密性(Confidentiality)
機密性とは、許可された人だけが情報にアクセスできるように管理することを指します。
対策例:社内システムにパスワードやアクセス制限をかけることで、第三者による不正アクセスを防げます。
完全性(Integrity)
完全性とは、情報が正しく保たれ、改ざんや破損のない状態を維持することを指します。
対策例:ファイルの変更履歴を残す、入力値に制限を設けるといった対策によって、不正な書き換えや意図しない修正を防止できます。
可用性(Availability)
可用性とは、必要なときに情報やシステムを問題なく利用できる状態を保つことです。
対策例:サーバーの冗長化や定期バックアップの実施により、トラブル発生時でも業務を継続しやすくなります。
この3要素が一つでも欠けると、情報漏洩やシステム障害のリスクが高まります。
それぞれの要素を意識し、適切な対策を取ることが重要です。
7要素とは?|追加された4要素
近年、テレワークやクラウド活用の広がりにより、3要素だけでは対応しきれないセキュリティ課題が増加しています。
そこで新たに4つの要素が加えられ、情報セキュリティ対策の枠組みは「7要素」へと拡張されました。
追加された4要素について、具体的な意味と対策例を見ていきましょう。
真正性(Authenticity)
真正性とは、情報の発信元が信頼できることを確認することを指します。
対策例:ログイン時に指紋認証やワンタイムパスワードを活用することで、なりすましを防ぎ、本人確認を強化できます。
責任追跡性(Accountability)
責任追跡性とは、誰が、いつ、どの情報にアクセスしたか、または操作したかを記録して追跡可能にすることを指します。
対策例:アクセスログを記録することで、不正行為が発覚した際の原因究明や責任の明確化に役立ちます。
否認防止(Non-repudiation)
否認防止とは、後から「やっていない」「知らない」と言い逃れができないよう、行動の証拠を確保することです。
対策例:重要なファイル送信時にデジタル署名を付けておけば、誰が送信したかを後から証明可能です。
信頼性(Reliability)
信頼性とは、情報システムが安定して動作し、必要なときに正確な情報を提供できる状態を保つことです。
対策例:サーバーを二重化したり、障害時の自動復旧機能を備えることで、システム停止のリスクを軽減できます。
それぞれの要素と対策については以下の表をご参照ください。
| 要素 | 適切な状態 | 対策例 |
|---|---|---|
| 機密性 | 許可された人だけが、情報やシステムにアクセスできる | 社内文書にパスワードを設定する、機密データを暗号化する |
| 完全性 | 情報が正しく保たれ、勝手に書き換えられない | ファイルの変更履歴を記録し、不正な書き換えを防ぐ |
| 可用性 | 許可された人が、必要なときに情報やシステムを利用できる | サーバーを複数用意して、故障しても使えるようにする |
| 真正性 | 本人以外がなりすませない | ログイン時に指紋認証や多要素認証を使用して本人確認を行う |
| 責任追跡性 | いつ・誰が・何をしたのか記録が残る | 操作ログを保存して、不正アクセスを調べられるようにする |
| 否認防止 | メール送信者や利用者が、後から関与を否定できないよう、証拠を残す | 重要なメールには電子署名をつけ、送信者の証明を可能にする |
| 信頼性 | システムが安定して動き、データが消えたりしない | 定期的にバックアップをとり、トラブル時に復元できる |
情報セキュリティの3要素が侵害されると?企業事例でリスクを解説
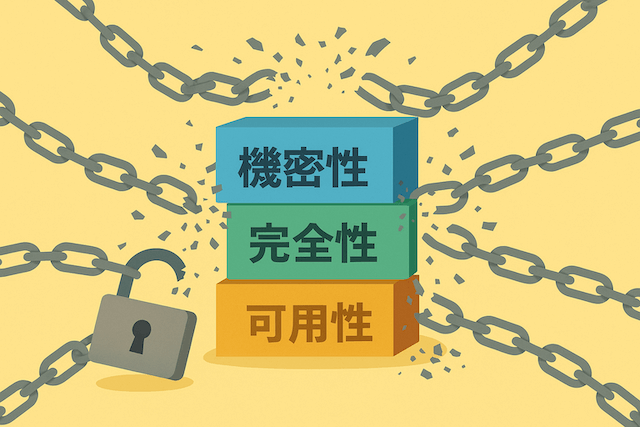
情報セキュリティの3要素は、企業が安定して事業を継続するための土台です。
しかし、いずれかが損なわれると、情報漏洩や業務停止など、企業の信用や経営に深刻な影響を与えます。
ここでは、実際に起きた事例をもとに、その影響について詳しく見ていきましょう。
機密性が侵害されたケース|個人情報流出による信用失墜と多額の損失
情報セキュリティの3要素の一つである「機密性」とは、許可された人だけが情報にアクセスできる状態を指します。
以下に企業の機密性が侵害された事例を紹介します。
事例1:ベネッセコーポレーションの顧客情報流出
概要:2014年、教育サービス大手のベネッセコーポレーションで約2,895万件の顧客情報が流出。
被害総額は約200億円に上るとも言われており、同社は情報管理体制の抜本的な見直しに着手しました。
原因:業務委託先企業の元社員が顧客データを不正に持ち出し、名簿業者に販売。外部委託先の情報管理体制の甘さが問題視されました。
(出典:ベネッセ 事故の概要)
事例2:尼崎市のUSBメモリ紛失による個人情報漏えい
概要:2022年6月、兵庫県尼崎市の住民約46万人分の個人情報が保存されたUSBメモリが一時紛失。
このUSBメモリには、氏名、住所、生年月日、マイナンバー、生活保護世帯や児童手当受給世帯の口座情報などが含まれていました。
原因:このUSBメモリは業務委託先の社員が無断で持ち出したもので、飲食店での紛失により発覚。 情報管理ルールの徹底不足が、大量の個人情報流出を招いた主な原因とされています。
(出典:尼崎市 USBメモリ紛失に関するお知らせ)
完全性が侵害されたケース|データ改ざんで業務が崩壊
「完全性」は、情報セキュリティの3要素のひとつで、データが正確に保たれ、外部からの改ざんや破損がない状態を意味します。
この完全性が失われると、記録や品質管理など業務の信頼性が大きく揺らぎ、企業活動全体に深刻な影響を及ぼすおそれがあります。
以下に、完全性が損なわれたことによって業務に大きな支障をきたした企業事例を紹介します。
事例1:旭化成建材による杭打ちデータ改ざん事件
概要:2015年、旭化成建材が施工を担当したマンションにおいて、杭打ち工事の一部で杭が強固な地盤に届いていなかったことが判明。
建物の傾きとして問題が表面化し、施工不良だけでなく、工事データの管理体制にも注目が集まりました。
原因:現場担当者が測定データの取得を怠り、過去のデータを流用して報告していたことが発覚。
この事態を受け、施工管理の透明性やチェック体制の不備が大きな課題として浮き彫りになりました。
(出典:旭化成建材株式会社 弊社杭工事に関するお詫びとお知らせ)
事例2:神戸製鋼所の検査データ改ざん事件
概要:2017年、神戸製鋼所が製造するアルミや銅製品などで検査データの改ざんが発覚しました。
これらの製品は航空機・自動車・鉄道などの重要インフラに使用されており、安全性への信頼を揺るがす深刻な問題となりました。
原因:厳しい品質基準や納期に追われる中、現場では検査データの書き換えが常態化していたとされます。
この事件は、品質管理体制の限界を浮き彫りにし、業界全体で再発防止策や運用体制の見直しを迫る契機となりました。
(出典:株式会社神戸製鋼所 不適切行為について)
可用性が侵害されたケース|システム障害で業務が停止
「可用性」は、情報セキュリティの3要素のひとつで、必要なときに正当な権限を持つユーザーが、情報やシステムを支障なく利用できる状態を意味します。
可用性が損なわれると、業務の継続に深刻な支障をきたし、顧客対応の停止や出荷遅延など、売上や企業信頼の低下にも直結するリスクがあります。
以下に、可用性が失われたことで大きな混乱を招いた事例を紹介します。
事例1:東京証券取引所の全銘柄取引停止
概要:2020年10月1日、東京証券取引所でシステム障害が発生し、全銘柄の株式売買が終日停止する事態となりました。
取引の終日停止は東証史上初の事例であり、その影響規模から「過去最大の障害」として大きく報道されました。
原因:売買システムのディスク装置が故障し、本来機能するはずのバックアップシステムが適切に作動しなかったことが原因でした。この事態を受け、システムの冗長性強化やバックアップ体制の見直しが進められました。
(出典:株式会社東京証券取引所 株式売買システムで発生した障害について)
事例2:江崎グリコの基幹システム障害による出荷停止
概要:2024年4月、江崎グリコは基幹システムの障害により、全ての冷蔵商品の出荷が停止する事態に陥りました。
原因:基幹システムを新しいものに切り替えた際にシステム障害が発生。企業はシステム移行時の検証プロセスを強化し、リスクを低減する対策を進めています。
(出典:江崎グリコ株式会社 基幹システム障害に関するお知らせ(PDF))
このように、情報セキュリティの3要素のいずれかが損なわれると、顧客からの信頼を失うだけでなく、業務停止や取引中断など深刻な経営リスクに直結します。
こうしたリスクを回避するには、自社のセキュリティ体制を定期的に見直し、弱点を見える化することが重要です。
まずは無料のセキュリティ診断を活用し、今あるリスクを正確に把握することから始めましょう。
情報セキュリティの3要素を守るために必要不可欠な対策
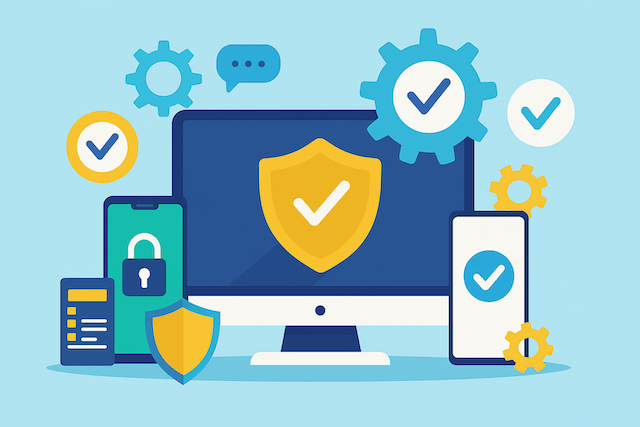
情報セキュリティの3要素を守るためには、機密性、完全性、可用性それぞれに適した対策が必要です。
では、具体的にどのような対策を講じるべきなのでしょうか?
本章では「機密性」「完全性」「可用性」の3つの視点ごとに、それぞれに適したセキュリティ対策を解説します。
機密性を守るために必要な対策
機密性を守るためには、不正アクセスを防ぎ、データの流出を防止することが重要です。
以下の対策を実施することで、情報漏えいのリスクを最小限に抑えることができます。
不正アクセス対策:ゼロトラストとMFA
不正アクセスを防ぐためには「誰が・どこから」アクセスするのかを厳格に確認することが重要です。
効果的な対策として、ゼロトラスト と 多要素認証(MFA) があります。
- ゼロトラスト:
「すべてのアクセスを疑い、常に認証を求める」考え方。内部ネットワークでもアクセスを厳しく管理し、不正侵入を防ぎます。 - MFA(多要素認証):
IDやパスワードに加え、別の要素(スマホ認証・指紋など)を組み合わせることで、不正ログインを防止します。
銀行ATMの「キャッシュカード(所有情報)+暗証番号(知識情報)」もその一例です。
ゼロトラストとMFAを組み合わせることで、不正アクセスのリスクを大幅に軽減し、企業や個人のセキュリティを強化できます。
データ暗号化:AES・TLSで保護
データ暗号化とは、情報を第三者に読み取られないように変換する技術です。
暗号化することで、万が一盗まれても内容を解読されにくくなります。
代表的な技術として AES(高度暗号化標準)とTLS(通信の暗号化)があります。
- AES:保存データを強力に暗号化し、不正アクセスを防ぎます。
- TLS:インターネット上の通信を暗号化し、盗聴や改ざんを防ぎます。
これらの暗号化技術を活用することで、データの機密性を確保し、不正アクセスや情報漏えいのリスクを低減できます。
内部不正対策:権限設計とアクセス制御
内部不正を防ぐためには「誰がどの情報にアクセスできるか」を厳密に制御する必要があります。
役職や業務内容に応じて最小限の権限を設定し、不要なアクセスを排除することで、情報漏えいのリスクを大幅に抑えることが可能です。
さらに、アクセス制限に加えてログイン履歴や操作記録を常時モニタリングすれば、不審な挙動の早期発見にもつながります。
こうした対策により、機密情報の不正な閲覧・持ち出しを防ぎ、企業の情報資産を堅牢に保護できます。
完全性を守るために必要な対策
完全性を守るためには、データの正確性を維持し、改ざんや誤変更を防ぐことが重要です。
以下の対策を実施することで、業務の信頼性を損なうリスクを低減できます。
改ざん防止:変更管理とログ追跡
業務データの正確性を維持するためには「いつ・誰が・何を」変更したかを明確に把握する体制が不可欠です。
バージョン管理ツールや監査ログを活用すれば、意図しない修正や不正な改ざんの痕跡を確実に残せます。
たとえば、重要なドキュメントや設定ファイルに対して変更履歴を残しておけば、元の状態への復元や差分の確認がスムーズに行えます。
このように、記録の透明性を高めることで、情報の完全性を維持しやすくなり、万が一のトラブルにも冷静かつ正確に対応できる体制が整います。
これらの対策は、不正な変更やデータ改ざんを未然に防ぎ、業務の信頼性を確保するうえで欠かせません。
加えて、法的要件やコンプライアンス対応にも貢献する重要な取り組みです。
完全性確保:定期監査の実施
定期監査は、データの正確性と信頼性を維持するために不可欠です。
定期監査を通じて、データの誤った更新や不正な改ざんを早期に発見し、修正できます。
また、監査により不正アクセスや内部不正からデータを守り、正確性を維持できます。
これにより、信頼性の高いデータ管理が実現し、業務の効率性とセキュリティが向上します。
可用性を守るために必要な対策
可用性を守るためには、システム障害やデータ消失に備え、常に安定した稼働を維持することが重要です。
以下の対策を実施することで、業務の中断や損害リスクを最小限に抑えることができます。
システム分散:安定稼働を維持
システムが1つだけでは、故障やトラブル時に業務が停止してしまうリスクがあります。
そこで、複数のサーバーを使用して負荷を分ける「ロードバランサー」や、複数のシステムを連携させる「クラスタリング」を導入することで、一部のサーバーが停止しても、他のサーバーが自動で処理を引き継ぎ、システムの運用を継続できます。
これにより、万が一の障害が発生しても、業務の中断を防ぐことができます。
バックアップと復旧:迅速なリカバリ
データが消失したり壊れたりすると、業務に大きな影響を与えます。
そのため、定期的なバックアップを取り、迅速なリカバリ体制を整えることが重要です。
特に、バックアップは別の場所(クラウドや外部ストレージ)にも保存し、復元手順を事前に定めておくことで、トラブル発生時にもスムーズに復旧できます。
これにより、データ損失からの業務再開を迅速に行えるため、ビジネスの可用性を高めることができます。
DDoS対策:WAFとCDN活用
DDoS攻撃とは、複数のコンピューターから大量のリクエストを一斉に送信し、サーバーをダウンさせることでサービス停止を狙うサイバー攻撃です。
このような攻撃を防ぐには、WAF(Webアプリケーションファイアウォール)を導入し、不審なアクセスを自動で遮断する仕組みを整えることが効果的です。
さらに、CDN(コンテンツ配信ネットワーク)を活用して、あらかじめ複数のサーバーにデータを分散しておけば、特定のサーバーへの集中負荷を軽減でき、攻撃耐性のある安定した運用を実現できます。
災害対策:BCPとDRの策定
災害や障害が発生しても業務を継続・復旧できるように、事業継続計画(BCP)と災害復旧計画(DR)の策定が欠かせません。
BCPは事業全体の継続計画、DRはシステムやデータの復旧手順に特化した計画です。
たとえば、定期的なバックアップと復旧手順の事前整備により、突発的な障害にも冷静に対応できます。
クラウド型のBCP・DRサービスも普及しており、自社の体制に応じて導入を検討しましょう。
企業の情報セキュリティを強化する具体策

サイバー攻撃や情報漏えいのリスクが高まる中、企業を守るには、セキュリティポリシーの整備、従業員教育、監視体制の強化が欠かせません。
本章では、こうした対策を効果的に実行するためのポイントを、実際の企業事例とともにわかりやすく解説します。
セキュリティ意識向上のための教育と実施方法
社員がセキュリティ知識を持たないまま業務を行うと、悪意あるメールを開封したり、脆弱なパスワードを使ったりと、企業の情報資産が脅威にさらされるリスクが高まります。
これを防ぐには、全社的にセキュリティ教育を徹底し、従業員一人ひとりの意識と対応力を高めることが不可欠です。
以下に、効果的な教育・訓練方法を紹介します。
- 1. 定期研修の実施
・eラーニングや対面研修を年2回実施し、基礎的なセキュリティ知識を習得
・重点テーマ:パスワード管理、フィッシング詐欺の見分け方など - 2. フィッシング訓練
・模擬フィッシングメールを定期送信し、開封状況をチェック
・開封者には個別フィードバックを行い、実践的な判断力を養成 - 3. 社内啓発活動
・社内ポータルを活用し、最新の脅威事例や注意喚起を定期配信
・実際に起きたインシデント事例を共有し、当事者意識を醸成
セキュリティ対策はシステムだけでなく「人の意識」に支えられています。
日常的な教育とトレーニングを通じて、従業員全体のリスク対応力を強化していきましょう。
企業のセキュリティポリシー策定と運用方法
企業全体の情報セキュリティを高めるには、ルールを定めるだけでなく、それを社員全員が理解し、実践できる仕組みづくりが不可欠です。
ここでは、効果的なセキュリティポリシーの策定・浸透・運用のために欠かせない取り組みを紹介します。
- 1. リスクに基づくルール設計
・「社外PCの利用制限」「機密データの暗号化」など、自社の業務リスクを踏まえた具体的なルールを明文化
・クラウド利用にはVPN接続を必須とし、アクセス制御を徹底 - 2. 社内への周知と定着
・新入社員研修での必須カリキュラム化
・社内ポータルにFAQや手順書を整備し、いつでも確認できる環境を提供 - 3. 定期的なポリシー更新
・半年ごとに見直しを実施し、脅威や技術の変化に対応
・生成AIの悪用リスクなど、新たな課題への対応ルールを随時追加
ルールは作るだけでは機能しません。
運用・教育・更新のサイクルを継続し、実効性のあるセキュリティポリシーを維持しましょう。
定期監査とリスク評価の実施による対策強化
セキュリティ対策が適切に機能しているかを確認するため、定期的な監査やリスク評価が欠かせません。
脆弱性を見える化し、必要な対策を継続的に講じることで、組織全体のセキュリティ水準を底上げできます。
- 1. 情報セキュリティ監査の実施
・ISO 27001の基準に基づき、管理体制の適切性を定期的にチェック
・外部の専門家による脆弱性診断で、潜在的リスクを早期に特定 - 2. リスクアセスメントの実施
・専用ツールを活用し、ネットワークやシステムの弱点を洗い出し
・リスクの重大度に応じて優先順位を設定し、効率的に対処 - 3. セキュリティインシデント対応計画の策定
・サイバー攻撃時の対応手順を明文化し、即時対応を可能に
・復旧フローや報告体制を整備し、被害の拡大を最小限に抑制
情報セキュリティは、企業の信用と事業継続を支える基盤です。
最新の脅威に対応し、強固なセキュリティ体制を維持することが求められます。
では、実際に「自社が今どの段階にあるのか」を確認するには、何から始めればよいのでしょうか?
まずは自社の現状を正しく把握することから
セキュリティ対策を強化する第一歩は、「現状を正確に把握すること」です。
どんな対策も、現状の課題やリスクを見誤っていては効果を発揮しません。
まずは、社内で以下のような項目をチェックしてみてください。
- セキュリティポリシーは策定され、運用されていますか?
- 従業員への教育は定期的に実施されていますか?
- 監査やリスク評価の体制は、実際に機能していますか?
こうした現状分析を通じて、次に取り組むべき課題や、優先すべき対策が明確になります。
企業のセキュリティ対策は「Office110」におまかせ!
この記事を通じて、情報セキュリティの3要素(機密性・完全性・可用性)の重要性や、対策についてご理解いただけたかと思います。
とはいえ──
「対策はしているつもりだけど、どこにリスクがあるのか不安…」
「専門家にチェックしてもらいたいけど、何から相談すればいいのか分からない…」
そんなお悩みはありませんか?
OFFICE110では、期間限定で「無料セキュリティ診断」を実施中!
- コストゼロで”潜在リスク”を可視化
- 専門コンサルタントが御社の状況を丁寧に診断
- 3要素別に「どこが弱点か」「何を強化すべきか」が明確に!
まずはお気軽に無料診断で現状チェックしてみませんか?
【今だけ無料診断】あなたの会社に最適なセキュリティ対策を専門家が提案!
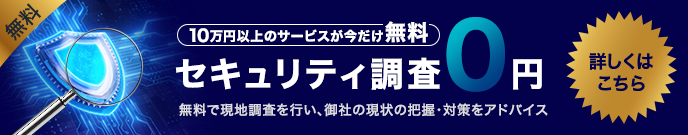
情報セキュリティ3要素の疑問を解決!よくある質問
最後に、情報セキュリティに関して、多くの企業が共通して抱える疑問をQ&Aで回答します。
Q1.情報セキュリティにおける「3大脅威」とは?(内部不正・外部攻撃・物理リスク)
企業の重要な情報は、主に以下の3つの脅威にさらされています。
- 1. 内部の人的ミス・不正
社員のミスや悪意による情報漏えいが発生することがあります。
例:メール誤送信、フィッシング詐欺、内部不正によるデータ持ち出し - 2. サイバー攻撃(外部からの脅威)
ハッカーやマルウェアによる不正侵入が情報資産を脅かします。
例:ランサムウェア感染、DDoS攻撃、不正ログイン - 3. 物理的リスク(災害・盗難)
自然災害や紛失・盗難によって、情報が失われる可能性があります。
例:火災・地震によるデータ消失、ノートPCの紛失、盗難被害
こうした3つの脅威に対応するには、内部不正対策・サイバー攻撃防御・災害対策の3本柱が必要です。
Q2.ISO27001とは何ですか?
ISO27001(アイエスオー27001)は、情報セキュリティの管理基準を定めた国際規格です。
企業がサイバー攻撃や情報漏えいのリスクを管理し、安全な運用を行うための仕組みを構築することを目的としています。
この認証を取得することで、適切なセキュリティ対策が実施されていることを客観的に証明でき、取引先や顧客からの信頼を得やすくなります。
Q3.ISMSとは何ですか?
ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)は、企業が情報を適切に管理するための仕組みです。
情報漏えいやサイバー攻撃のリスクを分析し、対策を実施・改善することで、継続的にセキュリティレベルを向上させます。
ISMSはISO27001に基づいて運用されるため、適切な管理体制を整えれば、ISO27001の認証取得も可能です。
ISMSを導入することで、情報資産の安全性を高め、企業の信頼性向上につながります。
また、ISMSの導入・運用は、第三者認証を受けずとも社内の情報セキュリティ体制強化に大きく貢献します。
まとめ:情報セキュリティ3要素を確保し、企業の信頼を守るために
本記事では、情報セキュリティの3要素「機密性・完全性・可用性(CIA)」と、拡張された7要素の概要や対策を解説しました。
サイバー攻撃や情報漏えいのリスクが高まる今、セキュリティ対策は”やっているつもり”では不十分です。
適切な対策を怠ると、被害の拡大や信頼の失墜に直結しかねません。
情報セキュリティは一度整備して終わりではなく、継続的な点検とアップデートが必要不可欠です。
まずは自社の「いまの弱点」を知ることから始めましょう。
✔️ 3要素の観点から、どこにリスクがあるのか?
✔️ 現在の対策で足りないのは何か?
こうした問いに答えるためにも、専門家によるセキュリティ診断の活用は有効です。